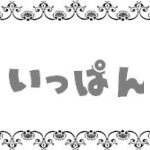現在サポートしてほしいこと
1.国土交通省の資料作成のサポート
国土交通省では、e-Stat 政府統計の総合窓口のデータを使ってデータ分析を行っています。
今後は統計ソフトも利用していくので、統計ソフトの調査、デモデータの作成、結果の表示などの作業をお手伝いして頂きたいと考えています。
統計ソフトは量的研究のマストアイテム
量的研究を進めるためには統計ソフトが必須です。量的研究とは、現象を統計によって予測・解釈し、意味ある結果を導出する方法です。量的研究では、数値化できるデータを収集・分析し、仮説を検証したり、関係性や傾向を明らかにしたりします。量的研究には臨床介入研究、観察研究、尺度開発研究などが含まれます。
これらはすべて統計ソフトがないと実施できません。統計ソフトとは、統計分析を行うためのコンピュータープログラムです。統計ソフトは、データの整理・管理・可視化・操作・変換・モデリング・推論などの機能を提供します。統計ソフトウェアには、HAD、JASP、PSPP、R、SAS、JAMOVIなどがあります。
統計ソフトウェアは量的研究において欠かせません。なぜなら、以下のような理由があるからです。
- 統計ソフトウェアは、大量のデータを効率的に処理できます。手作業では時間や労力がかかる作業も、統計ソフトウェアなら数秒で完了できます。
- 統計ソフトウェアは、様々な統計手法を適用できます。基本的な記述統計やt検定から、複雑な多変量分析や機械学習まで、統計ソフトウェアなら幅広い分析手法を利用できます。
- 統計ソフトウェアは、分析結果をわかりやすく表示できます。表やグラフやダッシュボードなどの形式で、分析結果を視覚的に表現できます。これにより、データの傾向やパターンや関係性を容易に把握できます。
以上のように、統計ソフトは量的研究を進めるために必須のツールです。統計ソフトウェアを使えば、データの収集・分析・解釈・発信がスムーズに行えます。統計ソフトの使い方を学び、量的研究のスキルを向上させましょう。
有料は高いうえに更新料も必要
統計ソフトウェアは量的研究を進めるために必須のツールです。しかし、有名なSPSSやSTATAは非常に高額です。しかもバージョンが更新されると、新しく買い直す必要があります。統計ソフトでいくらお金が溶けるかわかりません。なので、気軽に手が出せない人も多いです。そこで、無料の統計ソフトウェアに注目が行くわけです。
- 無料で高機能なおすすめ統計ソフト
- 無料おすすめ統計ソフト①:HAD
- 無料おすすめ統計ソフト②:JASP
- 無料おすすめ統計ソフト③:PSPP
- 無料統計おすすめソフト④:R
- 無料おすすめ統計ソフト⑤:SAS University Edition
- 無料統計ソフト6:JAMOVI
- 私の東京のお客様が年に1回か2回音楽会を行います。その際の受付、誘導等の案内係をお願いしたいと思います。
- ステップ1:テーマの設定と物語骨子の生成
- ステップ2:マンダラによる思考の構造化と可視化
- ステップ3:「言読」ツールによる原典の深掘り・分析
- ステップ4:探求結果を基にした新たな物語の創作
- ステップ5:マルチメディアコンテンツへの展開
- ステップ6:成果物の記録とコミュニティでの共有
無料で高機能なおすすめ統計ソフト
ただ無料で使える統計ソフトはいろいろあるけど、初学者にはどれを選べばよいかがわかりにくいものです。そこで、ぼくたちの研究室で実際に使用し、「これはよい!」と思った以下の無料の統計ソフトを紹介します。なお、統計ソフトを活用するためには統計の知識が必要です。
なお、統計ソフトを活用するためには統計の知識が必要です。統計の知識が不足している人は、統計おすすめ入門書をまとめた記事もお読みください。
>>【2020年】統計を独学したい人におすすめ書籍10冊+α【研究者が語る】
無料おすすめ統計ソフト①:HAD

統計ソフトHADとは、清水裕士先生が開発された、心理統計分析を行うためのフリーソフトウェアです。HADは、Microsoft ExcelのVBAで動いており、Excelさえあれば誰でも無料で使うことができます。HADは、基礎的な分析から統計的検定、分散分析、回帰分析、一般化線形モデル、因子分析、構造方程式モデル、階層線形モデルなどの多変量解析など多くの分析方法で解析が実行できます。
統計ソフトHADには、以下のようなメリットがあります。
- HADは、Excelで動くので、WindowsあるいはMacを利用している人なら誰でも使うことができます。
- HADは、心理統計分析に必要な機能を備えています。グラフや表を含むわかりやすい出力も可能です。
- HADは、随時更新されています。機能が増えたり、分析手法が追加されたりします。利用時には最新版をチェックしましょう。
無料おすすめ統計ソフト②:JASP

HADはとても使いやすいですが、仮説検定モデルのみに対応しています。 それに対してJASPは、近年たいへん注目されているベイズ統計にも対応しています。ベイズ統計とは、事前知識やデータから確率的に推論する統計的手法です。ベイズ統計では、仮説の妥当性やパラメータの信頼度を直感的に評価できます。
JASPには、以下のようなメリットがあります。
- JASPは、フリー、フレンドリー、フレキシブルの3つの特徴を持ちます。すなわち、誰でも自由に使えること、使いやすいインターフェイスを持つこと、様々な分析手法に対応していることです。
- 伝統的な仮説検定にも、ベイズ式の仮説検定にも対応しています。
- JASPはWindows,Mac,Linuxに対応しているので,お使いのOSにあわせてダウンロードしてください。
無料おすすめ統計ソフト③:PSPP

PSPPは有料のSPSSと同じ機能を実装することを目指して開発されている無料の統計ソフトウェアです。SPSSほど高機能ではありませんが、基本的な統計解析手法は実装されています。具体的には、記述統計、t検定、ANOVA、線形回帰、ロジスティック回帰、クラスタ分析、信頼性分析、因子分析、ノンパラメトリック検定などが行えます。
PSPPは簡単に使えるお勧めの統計ソフトであるものの、これを使うぐらいならHADやJASPを使ったらよいと思います、笑。
無料統計おすすめソフト④:R

説明不要なぐらい超有名なフリーの統計ソフトです。Rはそのまま使うのではなく、Rstudioで動かします。もちろんRstudioも無料です。Rは高機能かつ多機能で、拡張性が極めて高いです。ぼく個人はRをもっと良く使います。インターネットを調べると、たいていの使い方がわかりますし、解説書も非常に豊富です。
Rを使いながら統計について学ぶこともできますので、その方法に関心がある人は「【入門】未経験から「Rで統計解析」を目指す方へ【動画2本+書籍1冊】」を参考にしてください。
また、Rのパッケージにもいくつかオススメがありますので、興味ある人は「【医療者向け】R統計でおすすめのパッケージ3選【研究者が語る】」もあわせてお読みください。
RとRsudioはコードを書きますが、それを難しいと感じる場合はコマンダー系のRを使うとよいです。お薦めは改変R、EasyRなどです。
医療で必要な統計は一通りできます。
Rの書籍はたくさんでていますが、初学者には以下がお勧めです。

created by Rinker
¥4,576 (2025/09/21 00:39:41時点 楽天市場調べ-詳細)
無料おすすめ統計ソフト⑤:SAS University Edition

やや敷居が高いですけど、これも基本的な解析から非常に高度な解析までいろいろできます。以前、SASは高いイメージがありましたけど、いまや無料です。よい時代になりました。
University Editionと銘打っているので、学生しか使えないような印象を持ちがちですけど、実際には18歳以上の学生・社会人であれば誰でも使用できます。
個人利用と学術利用のみで商用利用は不可です。
>>SAS University Editionのダウンロードする
SASの書籍もいろいろありますが、以下の1冊が手元にあると便利かと思います。

created by Rinker
¥7,480 (2025/09/21 16:56:56時点 Amazon調べ-詳細)
無料統計ソフト6:JAMOVI
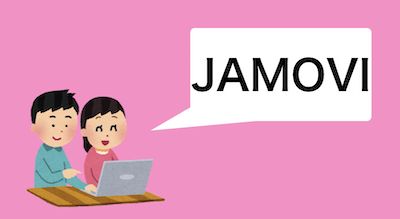
JAMOVIはJASP開発メンバーが開発した無料の統計ソフトです。
データ解析はRを活用しており、JAPSがベイズ統計を中心に開発されているのに対して、JAMOVIは柔軟な統計解析技術の活用を目指しているところに特徴があります。
対応しているデータ解析技術は記述統計、t検定、分散分析、反復測定分散分析、共分散分析、多変量共分散分析、ノンパラメトリック分散分析、相関分析、線形回帰分析、二項ロジスティック回帰、多重ロジスティック回帰、順序ロジスティック回帰、二項検定、適合度検定、分割表、信頼性分析、対数線形回帰、信頼性分析、主成分分析、探索的因子分析、確認的因子分析です(2018/10/29現在)。
結果はAPAスタイルに準拠した内容で出力されますし、なかなか便利です。
しかも、Rのスクリプトを表示させることもできるようです。
結局、どの統計ソフトを選べばよいのか??

以上、6つの統計ソフトを紹介しました。
後は皆さん自身で実際に操作し、目的にあっており、しかも使いやすいと感じる統計ソフトを選べば良いです。
とはいえ、皆さんの中には「特にお勧めを教えてくれ!」という方もいると思います。
結論:最強におすすめはR
結論をいうと、Rがもっともおすすめです。
理由は以下の通りです。
Rがおすすめの理由
- 完全無料である
- 自由に何でもできる
- 教材が豊富である
- どの統計ソフトからはじめても、最後はRを使いはじめる など
とにかく、Rが最強なので「特におすすめを教えろ!」と言われたら、マジでこれを推奨します。
「Rはちょっと難しそう」という人はHADとJASP
「Rはちょっと難しそう」という人は、ひとまずHADを選択してください。
HADはダウンロードしやすいし、マニュアルも充実しているし、操作が直観的なので、何をどう選べばわからない人でも使いやすいです。
また、簡単にベイズ推定を実行したい人はJASPを選んでください。
クリックするだけでベイズ推定ができるのは、JASPだけだからです。
慣れてきたら、ちょっとずつRに挑戦していきましょう。
くどいですけども、Rはプログラミングしないと駄目ですが、簡単なことから超複雑なことまで何でもできます。
2.プライベート音楽会の受付、誘導等
私の東京のお客様が年に1回か2回音楽会を行います。その際の受付、誘導等の案内係をお願いしたいと思います。
クラシック系の音楽に興味がある方、音楽界の受付、誘導等の案内係をお願いしたいと思います。
補助的に動画撮影なども、できればお願いしたいと思います。

お客様からの依頼によっては、外部ホールのコンサートの受付や裏方業務をお願いする場合もあります。
3.生成AIシステムの営業、講師などのお手伝い
開発している生成AIシステムは、単一のプロンプトで表層的な答えを生成する一般的なAIツールとは一線を画し、利用者が古典や哲学などの一次ソース(原典)に深くアクセスし、対話的に探求しながら、最終的に独自の物語やビジョンを体系的に構築することを目的としています。
この生成AIシステムの営業、講師などのお手伝いをして頂ければと考えています。
以下に、デモンストレーションで示された一連の操作手順を詳述します。
ステップ1:テーマの設定と物語骨子の生成
- 探求テーマの入力:
システムの入力フィールドに、探求したい中心的テーマや問いを自由なテキストで入力します。
- デモでの入力例: 叡智は進化するのか
- 物語骨子の自動生成:
テーマを送信すると、AIがその問いに関連する哲学、歴史、文学などの膨大な古典文献データベースから、核心的な概念を持つ8つの文章(断片)を自動で抽出します。
同時に、これら8つの要素を基盤とした「物語の骨子」を生成します。これには以下の要素が含まれます。
- 物語の仮題: 生成されるコンテンツ全体のタイトル案。(例:『叡智の螺旋 ―進化の果て―』)
- 中心テーマ: 物語を通じて探求するべき中心的な問い。
- 構成案(ストーリーライン): 8つの要素を論理的な順序で再構成し、起承転結のある物語の流れを提示します。
ステップ2:マンダラによる思考の構造化と可視化
- マンダラ形式での表示:
ステップ1で生成された結果は、マンダラ(曼荼羅)のフォーマットで視覚的に表示されます。
- 中央: 探求テーマが配置されます。
- 周囲: 抽出された8つの古典文献からの引用が、物語の展開順(「の」の字を描くように)に配置されます。
- 原典へのアクセス:
マンダラ上の各要素はインタラクティブになっており、クリックすることでその引用が含まれる原典のタイトルや著者、文脈などの詳細情報を確認できます。これにより、全てのアイデアがどの一次ソースに基づいているかを常に把握できます。
ステップ3:「言読」ツールによる原典の深掘り・分析
思考の核となる、原典を深く読み解くための専用ツールです。
- 分析対象の選択:
マンダラから抽出された8つの文章の中から、特に深掘りしたい一文を選択します。 - 多角的なAI解析:
選択した一文に対し、AIが以下の多角的な分析結果を提示します。
- 文脈を考慮した翻訳: 単なる直訳ではなく、その文献の哲学的背景や文脈全体を考慮した、精度の高い翻訳を生成します。
- 文法・語彙の分解解説: 特に古典ギリシャ語やサンスクリット語などの原典の場合、文章を単語レベルまで分解し、それぞれの品詞、格変化、語源などを詳細に解説します。これにより、言語習得者でなくても原典の構造を深く理解できます。
- 哲学的解説: その一文が持つ哲学的な意味、歴史的な意義、そして探求テーマ全体の中でどのような役割を果たすのかを解説します。
- 対話による探求: 利用者はAIに対して、特定の単語(例:エネルゲイアとは何か)や概念について追加の質問を投げかけることができます。AIは家庭教師のように対話形式で回答し、理解を深める手助けをします。
ステップ4:探求結果を基にした新たな物語の創作
原典の深い理解を基に、オリジナルの創作活動へ移行します。
- 物語の設計図(フレームワーク)設定:
生成したい物語のジャンル(例:SF、ファンタジー)、登場人物、時代背景、舞台設定などを指定します。この設計図自体を編集することで、出力される物語の方向性を自由にコントロールできます。 - 物語の自動生成:
設定した設計図と、ステップ3までの探求で得られた哲学的な知見を統合し、AIが新たな物語を創作します。
- デモでの生成例: 『星辰図の錬金術師』というタイトルのSF物語
- 出力内容: ログライン(物語の要約)、登場人物設定、三幕構成(序盤・中盤・終盤)に基づいたプロットなどが含まれます。
ステップ5:マルチメディアコンテンツへの展開
生成された物語を、文章以外の多様なメディアへ展開します。
- シーン分割と絵コンテ生成:
物語全体を具体的なシーンに分割し、各シーンの情景を描写します。
その描写テキストをプロンプトとして、DALL-Eなどの画像生成AIツールに入力することで、絵コンテやコンセプトアートを視覚的に作成できます。 - 音楽・音声コンテンツの生成:
物語の雰囲気やテーマに合わせたBGMや効果音のコンセプトを提示します。これをSunoなどの音楽生成AIに入力することで、オリジナルの楽曲を作成することも可能です。ナレーション原稿を生成し、音声合成にかけることもできます。
ステップ6:成果物の記録とコミュニティでの共有
- 研究ノートの自動生成:
ステップ1から5までの全プロセス(探求テーマ、原典分析、問答の記録、創作した物語など)は、一つのドキュメント(Googleドキュメント形式)として自動的にまとめられ、「研究ノート」として保存されます。
コミュニティでの共有:
完成した研究ノートや創作物語は、ボタン一つでシステム内のコミュニティプラットフォームに共有できます。他の利用者がどのような探求を行い、どのような物語を創作したか閲覧することで、新たな着想を得るきっかけとなります。